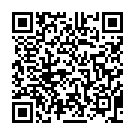分類
2021年01月15日(金)
校長の授業潜入記89
校長です。
明日は共通テスト。
それに備えて3年生は今日は午前授業でした。
こちらは共通テスト前の最後の授業(4限目)。
今やっているところが出るといいんですけど。
3年生の健闘を祈ります。さて,試験も終わって授業再開。今日も「撮れ高」十分でしたが,その中からこちらを。
これは2年生の家庭科(調理実習あるところに校長あり)。
時節柄,家庭科の先生が細心の注意を払って対策をして実施していました。本日のメニューは「お弁当」でした。
ついこの間は被服実習で七転八倒していました(失礼)が,今日は調理実習で四苦八苦していました(またまた失礼)。
慣れている生徒もいる一方で,手つきが化学の実験のようだったり,エプロンはもうちょっと引き上げた方がいいかもと思ったり,できあがりが「ワイルドだろ~」(・・・すみません。)だったりと,まぁ,画的にはバリエーションに富んだ感じとなりました。(ちなみに,今回のご飯は,災害時のための学習も兼ねて,ビニール袋に米と水を入れてお湯で炊くという方法で作っています。)でも,自分で作ったもの,しかも作りたてっておいしいんですよね。
感染症対策のため,みんなでテーブルを囲んで,というのはできませんでした(食事は教室でした)が,いつかできるといいですね。2021年01月14日(木)
3年共通テスト説明会・自動車学校入校説明会
7校時,今週末に実施される共通テストの説明会が行われました。
これまでに積み重ねたものを十分に発揮してがんばってください。同じ時間に自動車学校の入校説明会も実施されました。
こちらは,指宿中央自動車学校の方から丁寧な説明をしていただきました。2021年01月14日(木)
1・2年生 薬物乱用防止教室
7校時,指宿警察署生活安全刑事課の川前さんを講師としてお招きし,薬物乱用防止に関する教室を開催しました。
少年の薬物乱用に関し,インターネットを通じ,安易に手を付ける実態など,様々なお話をしていただきました。情報が氾濫する中,正確な情報をもとに,正しい判断をすることで自分の身を守ることの大切さを再認識させられました。2021年01月12日(火)
校長の校内探訪記31
校長です。
学校を飛び出して(嫌なことがあったわけではありません),指高生がボランティアに参加しているという山川の福元公民館に出かけてみました(もう「校内」探訪ではなくなっていますが・・・)。
これは,冬休みを利用して(この日は1/5)児童クラブに来る子どもたちと一緒に様々な活動(遊び相手など)をするというボランティアです。
このときは男子2人が,パソコンを使ったゲームの遊び方を教えているところでした(直前まで鬼ごっこをしていたということですが,カメラマン的にはこちらの方が助かります)。
将来教育に携わりたいと考えている生徒にとってはこういう機会をいただけるのはありがたいことです。
今後も,高校生が参加できる活動があれば,お声がけをいただければありがたいです。
この冬休み期間中,1,2年生の男女あわせて20人が,この活動に参加させていただきました。参加してくれたみんなもありがとう。
2021年01月12日(火)
「かごしまおいしいもの選手権」入賞!
令和2年度「かごしまおいしいもの選手権」
県では,地産地消の取組を推進するため,県民の県産農林水産物・県内農林水産業への理解促進を図っています。その取組の一環として,県内高校生等を対象に,県産食材を活用したメニューコンテストを開催しています。
今年度は,応募総数104作品の中から,書類審査,試食・プレゼンテーション審査を経て,入賞作品12点が決定し,3年生フードデザイン選択者の作品も選ばれました。
さらに,谷山のおいどん市場「農家レストランたわわ」で毎週木曜日に提供されることが決定しました。
【入賞:スイーツ部門】

オクラちゃーずケーキ
(指宿高等学校 Love so sweetsチーム)
審査会の様子
令和2年11月18日(水曜日),かごしま県民交流センターにおいて,試食とプレゼンテーションによる審査が実施されました。県内8校から22人の高校生が参加,県産食材を生かし,工夫を凝らした作品とプレゼンテーションを披露しました。


木曜日,谷山のおいどん市場「農家レストランたわわ」のお近くにお立ち寄りの際はぜひ。
2021年01月08日(金)
3学期始業式
新年,明けましておめでとうございます。
今日から3学期スタートです。強い寒波が襲来したため,始業式は校内放送により,各ホームルームで実施するようにしました。
その後は,大掃除,実力考査(3年生は授業)でした。

来週末はセンター試験です。3年生は自分の進路達成のための追い込みに入っています。1・2年生もあとに続こう!
12日(火)は,1・2年生が実力考査,3年生は通常授業になります。
2021年01月08日(金)
校長の校内探訪記30
校長です。
2021年が始まりました。
これは学校に届いた年賀状・・・ではなくて,書道の時間の作品です。
新春らしい雰囲気を漂わせてくれています。そして,今日から3学期の始まりました(始業式はたぶん公式で上がるので割愛します)。
そして,いよいよ来週の土日(1/16,17)は共通テストがあります。
3年生は直前とあって,自習にも緊張感が漂います(1/5の様子)。
指高生の大成功を祈ります。
皆さんも応援してください。新春第1号なので厳かな感じで終わりたいと思います。
今年もよろしくお願いします。2021年01月06日(水)
がんばっています 指宿高校
先輩の声や成績伸び率,進路情報をまとめてみました。みんな自分の進路実現を目指し,一生懸命がんばっています。頑張る姿を生徒同士が互いに認め合い,教師が全力でバックアップする体制が指宿高校にはあります。今,指宿高校を目指している中学生の皆さん,コロナに負けず,がんばってください。皆さんの入学を待っています。
2021年01月06日(水)
コロナ対策,もう一度チェックを
中学生のみなさんへ 入試までの注意事項[PDF:120KB]
令和2年12月18日に文部科学省・厚生労働省が,高校生向けに,新型コロナウイルス感染防止のための注意事項を発表しました。
中学生向けにチラシを作りましたので,ぜひお読みください。
2020年12月25日(金)
本と楽しむクリスマスコンサート
今日はクリスマスイブ。指高サンタから素敵なプレゼントが届きました。
「本と楽しむクリスマスコンサート」はじまりはじまりー!
第一部はクリスマスコンサートです。まずは,吹奏楽部の演奏からどうぞ
クリスマスソングを中心に,宇宙戦艦ヤマト,勇気100%,笑点のテーマなど,最後にはみんなが手拍子がでるほど盛り上がり,たくさんのサンタクロースから楽しいひと時がプレゼントされました。
続いて,図書部によるクリスマス絵本の読み聞かせです。音声はないですが雰囲気を味わってください。
いわさきちひろ・名作えほんより「あおいとり」の読み聞かせです。図書部の生徒と福冨先生が声優となりそれぞれの役を演じました。プロの声優かと思うくらい質が高く,皆があおいとりの世界に引き込まれていきました。
1部終了です。
ところで,今回は密を避けるため,別会場でリモート視聴会を生徒会が準備してくれました。
リモート会場へ移動中,3年生が受験に向けて自主学習に励んでいる姿がありました。集中力半端ないです。
休憩が終わり,第2部のスタートです。
3年2組総選コース現代社会選択者による指宿地区の民話「蛇になった娘」の読み解きで,紙芝居「花タンゴ」を鹿児島弁満載で披露してくれました。
生徒んしは,じさんたっが使こかごんま弁でいっぺこっぺきばっちょったど。地域の民話をよかふに伝えっくれっせーあたいもわっぜー嬉しかったがよ。そん後に福冨先生と米倉先生の説明があったでさらにわかい易かったがよ。まこて良か時間をもろてあいがとさげもした。
帰りに紺屋サンタと福冨サンタからのささやかなプレゼントをもらって生徒たちは嬉しそうでした。
図書委員長で司会の2年1組栫井くるみさんに,感想をもらいました。
「リモートは初めてなので,準備にてこずって時間が伸びたりして苦しかったけど,成功できて良かった。来年も後輩には頑張ってほしい。生徒の皆さん来てくれてありがとうございました。」